デジタルデトックスとは?やり方と疲労や健康への影響
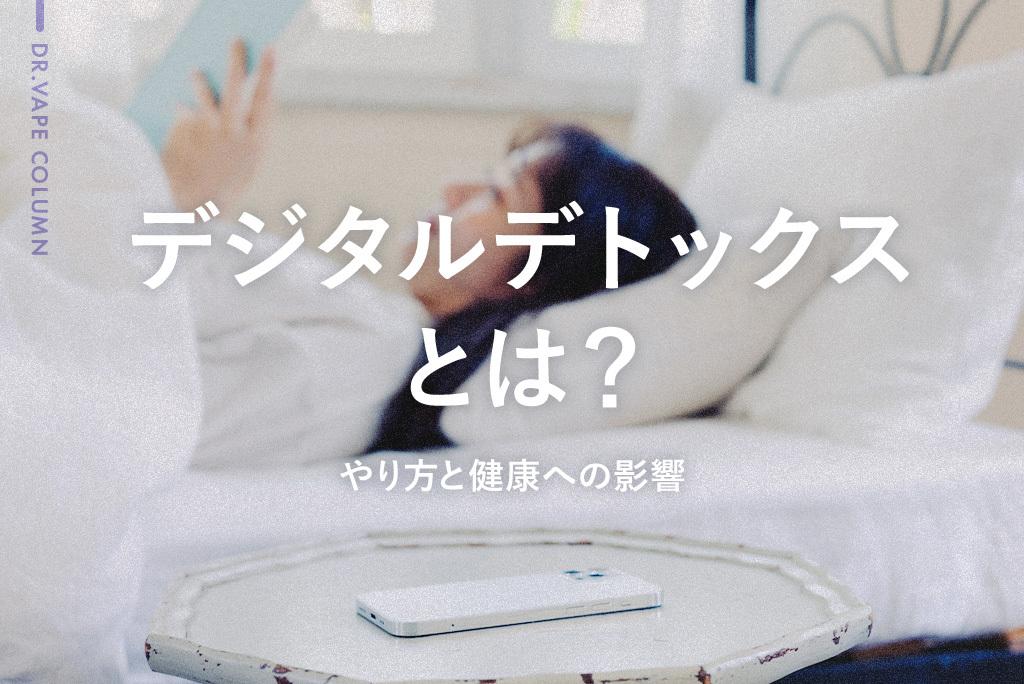
デジタルデトックスとは、スマホやパソコンなどのデジタル機器から意識的に距離を置き、心身をリフレッシュする方法です。
デジタル機器への依存が強まる現代社会では、情報過多による脳の疲労が心身の不調を招く要因のひとつとなっています。
本記事では、デジタルデトックスの意味や効果、すぐに始められる実践方法、そして健康への影響について分かりやすく解説します。
デジタルデトックスとは

デジタルデトックスとは、スマホやパソコン、タブレットなどのデジタル機器から意識的に離れ、心身をリセットする方法です。
現代社会では、一日に多くの時間をSNSやメール、動画配信サービスなどの画面を見ながら過ごすことが当たり前になっています。
その結果、脳が処理しきれないほどの情報にさらされ、集中力の低下や睡眠の質の悪化、さらにはストレスの蓄積を招いているのです。
現在実施中のキャンペーン

デジタルデトックスの効果とメリット

デジタルデトックスは、情報過多で疲れた脳を休ませ、集中力の低下や睡眠の質の悪化といった不調を改善する手助けとなります。
ここでは、デジタルデトックスがもたらす以下の効果とメリットについて解説します。
- 脳と心がリフレッシュされる
- 睡眠の質が向上する
- 集中力と生産性が上がる
- 人とのつながりが深まる
- 時間を大切にできる
脳と心がリフレッシュされる
デジタル機器から距離を置き、一時的に情報量を減らすことは、思考を整理するうえで効果的です。
頭に入ってくる情報が減ると、思考や行動を司る前頭葉が休息モードに切り替わり、脳が本来の働きを取り戻せます。
また、影響力の大きいSNSから距離を置けることも、デジタルデトックスの大きなメリットです。SNSは「自分には魅力がない」と感じさせたり、不安やうつといった精神的負担を引き起こす可能性が指摘されています。
デジタルデトックスによってこうした比較や評価から離れることで、心理的な負担が軽くなり、不安や焦燥感の緩和につながります。
参考:「Digital detox as a means to enhance eudaimonic well-being」(Frontiers in Human Dynamics)、「デジタルデトックスとは?」(一般社団法人日本デジタルデトックス協会)、「デジタル機器及びソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)の使用がメンタルヘルスに与える影響の解明のための研究」(厚生労働省)
睡眠の質が向上する
デジタルデトックスは、スマホやパソコンの画面から放たれるブルーライトを遮断できるため、睡眠の質を高める効果が期待できます。
ブルーライトを夜遅くまで浴び続けると、脳が昼間だと錯覚し、体内時計を整える「メラトニン」という睡眠ホルモンの分泌が妨げられます。
これにより、寝付きが悪くなったり、眠りが浅くなったりするのです。
就寝の1時間前にはデジタルデバイスの電源を切り、暖色系の照明の下で過ごすのがおすすめです。
強い光や情報による刺激が減ると、活動を促す交感神経が落ち着き、副交感神経が優位になって深い眠りに入りやすくなります。翌朝も軽やかに目覚められるでしょう。
参考:「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」(厚生労働省)
集中力と生産性が上がる
デジタルデトックスを行うと、絶え間なく入ってくる情報が減るため、分散していた意識が一点に集中し、作業への没入度が高まります。
脳が情報処理の負担から解放されることで疲労が溜まりにくくなり、思考力や判断力が持続するため、タスクを効率的に進められるようになるのです。
また、頭の中が整理されることで、埋もれていたアイデアが浮かびやすくなります。これにより、限られた時間でもアウトプットの質が向上し、生産性全体の底上げにつながるでしょう。
参考:「Digital detox as a means to enhance eudaimonic well-being」(Frontiers in Human Dynamics)、「デジタルデトックスについて中小企業でできることを教えてください。」(独立行政法人中小企業基盤整備機構)
人とのつながりが深まる
デジタルデトックスを行うと、これまで画面を見ていた時間を、家族や友人との会話にあてられるようになります。
デジタル機器に触れないことで、相手の声や表情に意識を集中でき、自然と相手に寄り添えるようになるでしょう。
相手の微妙な仕草や沈黙といったニュアンスも感じ取れるようになるため誤解も減り、相手の本音を引き出しやすくなるのも利点です。
相手と過ごす時間への満足度が高まり、日常における安心感や幸福感の向上にもつながります。
参考:「Digital detox as a means to enhance eudaimonic well-being」(Frontiers in Human Dynamics)、「デジタルデトックスについて中小企業でできることを教えてください。」(独立行政法人中小企業基盤整備機構)
時間を大切にできる
デジタルデトックスを行うと、SNSやメールの通知といった注意を散漫にさせる情報から解放され、限られた時間をより有意義に使えるようになるのです。
デジタル機器をいじりながらの「ながら行動」が減るため、優先すべき課題や人間関係など、一つひとつの行動に集中できます。
その結果、勉強や運動、家族との対話など「本当にやりたいこと」に時間を充てられるようになり、生活全体の満足度が高まるでしょう。
デジタル機器が体に与える影響とは?デジタルデトックスが必要な理由

パソコンやスマホなどデジタル機器の普及により私たちの生活は便利になりましたが、その陰で心身に想像以上の負担がかかっていることをご存じでしょうか。
長時間にわたるデジタル機器の使用は、眼精疲労や情報過多による集中力の低下など、さまざまな悪影響を私たちの体に及ぼします。
ここでは、デジタル機器が体に与える代表的な4つの悪影響について解説します。
- 眼精疲労と近視が進む
- 頭痛・肩こり・首のこり(スマホ首)を発症する
- 睡眠の質が低下する
- 情報疲労による集中力の低下を招く
眼精疲労と近視が進む
デジタル機器の長時間使用は、眼精疲労や近視の進行を招くリスクがあります。
ディスプレイを集中して見続けると、目のピントを調整する毛様体筋が緊張し続けるため、眼球が休めず酷使されてしまうからです。
この状態が続くと、かすみ目やドライアイが起こりやすくなり、最終的に視力低下につながります。
実際、約33万人を対象としたある研究では、画面を見る時間が1日1時間増えるごとに、近視になるリスクが21%も上昇すると報告されています。特に成長期の子どもは影響を受けやすいため、画面の凝視による目の乾燥などには注意が必要です。
参考:「Digital Screen Time and Myopia A Systematic Review and Dose-Response Meta-Analysis」(JAMA Network Open)
頭痛・肩こり・首のこり(スマホ首)を発症する
スマホやパソコンの使いすぎは、頭痛や肩こり、首のこり(スマホ首)の原因となります。
これは、視線が下向きになることで頭が前に突き出し、首の自然なカーブが崩れてしまうためです。
首にかかる負担は通常の4〜6倍に達し、筋肉が常に緊張状態になることで、これらの症状を引き起こします。
厚生労働省が3,000人以上を対象に行った調査では、コンピューター使用者の68.9%が何らかの症状を訴え、そのうち23.3%が頭痛を報告しています。
長時間の前かがみ姿勢は血流を悪化させ、腕のしびれなどの症状を招くおそれもあるため、定期的に姿勢を正すことが重要です。
参考:「デジタルデバイスが若年者の身体に与えている影響の現状」(公益財団法人宮崎県健康づくり協会)、「ストレートネック ~今話題の健康ワード!~」(日本成人病予防協会)
睡眠の質が低下する
スマホやパソコンなどデジタル機器のブルーライトは、睡眠の質を低下させる原因となります。
ブルーライトを浴び続けると、体内時計が乱れて睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌が抑制されるためです。
この影響で、入眠が遅れたり、眠りが浅くなったりします。さらに、SNSや動画視聴から得る情報が脳を興奮状態にさせ、深い睡眠を妨げます。
実際、若者を対象とした調査では、就寝前にSNSを利用する時間が長いほど、睡眠の質が悪化し、不眠症になる傾向があることがわかっています。
参考:「Vol.43 睡眠不足とブルーライト」(地方独立行政法人筑後市立病院)、「Mechanisms Linking Social Media Use and Sleep in Emerging Adults in the United States」(Behavioral Sciences)
情報疲労による集中力の低下を招く
デジタル機器から絶えず情報を受け取り続けると、脳が処理能力を超えてしまい、情報疲労による集中力の低下を招きます。
スマホが近くにあるだけでも、脳は常にその存在を意識し、エネルギーを分散させてしまうものです。
その結果、ミスが増えたり、パフォーマンスが低下したりと、質の高い作業を長時間続けることが難しくなります。
実際、アメリカの大学生を対象とした実験では、スマホを別室に置いたグループの方が、持っていたグループよりも記憶力や集中力テストの成績が有意に高いという結果が出ています。
参考:「「スマホを見続ける」習慣は脳にNG? 今すぐ脳を救出し、最強脳へ育てる運動の法則」(公益財団法人日本財団)
デジタルデトックスの方法

デジタルデトックスを成功させるには、ただ闇雲に端末を遠ざけるのではなく、まず現状を把握し、自分に合った無理のない方法から始めましょう。
生活リズムに合わせて少しずつ実践を重ねることで、スマートフォンなどのデジタルデバイスと健全な距離感を築けるようになります。
- 使用状況を知る
- 通知オフにする時間を作る
- ながら見をやめる
- デジタル機器を物理的に遠ざける
- 代わりの習慣を持つ
使用状況を知る
デジタルデトックスを始める第一歩として、まずは自分がどれだけデジタル機器を使っているかを把握しましょう。
使用状況を客観的に知ることで、減らすべき時間や優先的に見直す習慣が明確になり計画を立てやすくなります。
スマホやパソコンには、アプリごとの利用時間や回数を記録する機能が備わっています。
まずはこれらを確認し、どの時間帯にどれくらい使っているのかを可視化しましょう。
通知オフにする時間を作る
一日の中で一定時間は、スマホやパソコンの通知をオフにする習慣を持ちましょう。
通知が入らない環境を意図的に作ることで、作業に集中できるだけでなく、心が落ち着き、情報に追われる感覚からも解放されます。
まずは30分程度から始め、慣れてきたら1時間など、自分に合った長さに伸ばしていくと続けやすくなります。
ながら見をやめる
デジタルデバイスの「ながら見」は、脳に同時に複数の作業をさせてしまい、疲れが溜まりやすくなるため控えましょう。
食事中や会話中にスマートフォンやテレビを見続けると、目や脳が常に情報処理を強いられます。これにより集中力がそがれるだけでなく、一緒にいる相手や出来事への関心も薄れ、満足感が低下してしまうのです。
意識的にデバイスから目を離し、一つの行動に専念することで、心の余裕が生まれ、日常の充実度も高まります。
デジタル機器を物理的に遠ざける
デジタル機器を物理的に遠ざけると、端末に手が触れるまでの距離が「ブレーキ」となり、無意識に触る癖を抑えやすくなります。
「どのタイミングで・どこに置くか」を決めて、デジタルデトックスを実践してみましょう。
帰宅後はスマホを玄関に置く、就寝90分前からは寝室に持ち込まないなど、置き場所を固定して使わない時間帯を明確にすると効果的です。
視界からデジタル機器が消えるだけで通知への条件反射が弱まり、脳がリラックスモードに切り替わりやすくなります。
代わりの習慣を持つ
効果的にデジタルデトックスを持続するには、端末を見る代わりになる習慣を持つことが大切です。
本を読む、近所を15分歩く、思いつきをノートに書き出すなど、あらかじめ代わりの行動を決めておくと、その時間が楽しみに変わります。
軽いストレッチや瞑想、料理の下ごしらえなど五感を使う習慣もおすすめです。
新しい行動を積み重ねるほど、デジタルデバイスへの依存は薄れ、無理なくデジタルデトックスを長く続けられるようになります。
現在実施中のキャンペーン

デジタルデトックスを取り入れた人が感じた変化とは? 独自調査で見えた効果

今回、デジタルデトックス経験者10名に独自アンケートを行いました。
実施期間は「1日の中の数時間」が50%、「1日程度」が40%、「1週間以上」が10%で、短期集中型が大半を占めています。
デトックス中に制限したものは、時間を消費しやすい「YouTubeなどの動画視聴」が最も多く、次いで「SNS(Instagram、X、TikTokなど)」、「メールやLINEなどのメッセージツール」、「スマホで作業できるもの全て」という結果でした。
|
調査データ 調査対象:20~60代の男女10人 調査内容:デジタルデトックスに関するアンケート 調査方法:インターネット調査 調査期間:2025年8月1日~8月10日 |
デジタルデトックスで得られた効果
今回のアンケートで、最も多かった回答は「スマホを触らないことで生まれた自由な時間を有効活用できた」という変化です。
▼男性/40代/デジタルデトックス期間:1日のうちに数時間
| 時間を有効に使えるようになった。テレワーク中心の仕事柄、自分の生活がいつもインターネットに振り回されているような気がしていたが、しばらくデジタルデトックスを実施したら一日の時間を自分の意志で自由に選択できるようになってとても気分がスッキリした。 |
続いて「情報から離れて心が軽くなりストレスが減った」、「睡眠の質が向上した」、「目の疲れや頭痛が軽減した」が2人という回答結果になりました。
▼男性/40代/デジタルデトックス期間:1日から3日
| スマホを利用すると情報量が多いので、それが疲れやストレスの原因だったのだと気づいた。数日とはいえ、デジタルデトックスをしたことで精神面での変化は自分でわかるほど実感できた。 |
▼女性/50代/デジタルデトックス期間:1日のうちに数時間
| 睡眠の質が上がりました。夜中にスマホを見なくなっただけで、入眠がなめらかになったように感じて、朝の目覚めが少し楽になりました。 |
メリットを実感し再挑戦したい人が多数
デジタルデトックスに取り組んでいる最中は、「反射的にスマホを手に取ってしまいそうになった」、「調べものができなくてもどかしかった」、といった戸惑いもあったとのことです。
その一方で、回答者の80%が「今後も定期的に取り入れたい」「時間があればまた挑戦したい」と答えており、多くの方がメリットを実感していることがわかります。
実践の際には、本記事で紹介した方法をぜひ参考にしてみてください。

仕事の合間や読書のブレイクなど、デジタルデトックス中のひと息には電子タバコのDR.VAPEがおすすめです。
好きな香りを楽しみながら深く吸って吐くことで、自然と呼吸に意識が向き、頭をリセットしやすくなります。
ニコチン・タールゼロでありながら満足感のある吸いごたえがあり、気分を切り替えてリフレッシュするサポートとしてデジタルデトックス中にもおすすめです。
フレーバーは9種類あり、スイーツ系からタバコ風味まで、好みに合う一本がきっと見つかります。
|
ワイルドビター たばこ独特の甘さと苦みを表現 
|
クラシックスモーク スモーキーで吸い心地がよいタバコ味 
|
ミントメンソール すっきり爽やかなメンソール味 
|
|
ピュアアップル 甘さにキレのあるアップル味 
|
ジューシーマスカット 芳醇な甘さがあふれるマスカット味 
|
リラックスバニラ コクのある味わいと濃厚なバニラの香り 
|
|
クリーミーバナナ まろやかで濃厚なバナナの味わい 
|
トロピカルマンゴー 南国のマンゴーのようなジューシーな味 
|
ミックスベリー フレッシュで甘酸っぱい3種のベリーを表現 
|
2024年発売の最新モデル「DR.VAPE Model 3」は、フレーバーに天然由来成分のβ-カリオフィレンを配合。
β-カリオフィレンは、吸うことで心身を穏やかに整えたい方に注目されている成分です。
さらにDR.VAPEは、LINEからいつでも解約できる定期購入プランが用意されており、予算や使用ペースに合わせて無理なく続けられる点も魅力です。
デジタルデトックスの時間をより充実させるパートナーとして、DR.VAPEを取り入れてみませんか。